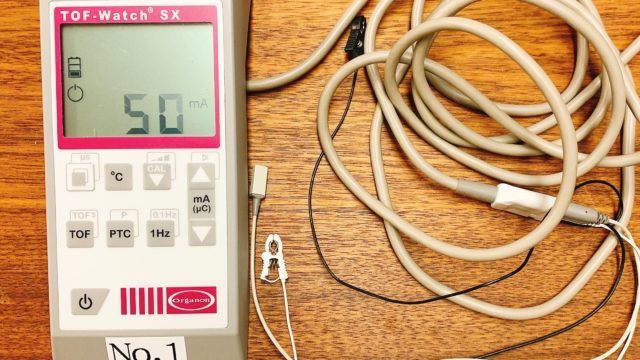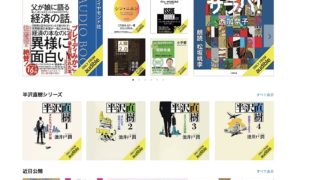このページを読むと解けるようになる(!?)問題
⬇️ご覧の通り、出題数が多いのでしっかりおさえていきましょう!ᕦ(ò_óˇ)ᕤー
①輸血製剤の保存・保管、輸血準備、その他(このページ)
- 2019-A41
- 2018-A56
- 2017-A7
- 2017-A55
- 2017-B6
- 2017-B17
- 2016-A10
- 2016-B49
- 2014-A18
- 2014-B41
②膠質液(このページ)
- 2019-B5
- 2014-A17
③各種自己血輸血(次の投稿)
- 2019-A41の一部
- 2018-A56
- 2016-A9
- 2016-B49の一部
- 2014-A19
④輸血副作用(次の投稿)
- 2019-A26(TRALI)
- 2018-A56(GVHD)
- 2017-A55の一部
- 2017-B17の一部
- 2016-B7(不適合輸血)
- 2015-B22
⑤異型輸血(次の投稿)
- 2019-A27
- 2015-B49
- 各種血液製剤の保管・保存方法について
- 各種輸血製剤の投与基準について
- 輸血準備に関わる内容について(T&S、MSBOS、SBOE)
- コロイド製剤の選択
各種血液製剤
とりあえず麻酔科研修や周術期管理チーム試験では、基本である赤血球濃厚液(RBC)、新鮮凍結血漿(FFP)、血小板濃厚液(PC)の3つをおさえておきましょう。それぞれの保存・保管方法、投与基準の目安が問われています。
また、当然ですが、輸血やアルブミンなどの血液製剤の投与には「同意書」が必要ですので、必ずチェックするように!(今は同意書の確認も照合も電子カルテでできるので楽になりました🤗)
同意書がない場合は主治医にきちんと連絡しましょう。
赤血球濃厚液(RBC)
供血(提供された血液)400ml由来で、1パックあたり約280mlです。この1パックで2単位です。よく「赤4単位オーダーして」とかいいますよね。
赤血球濃厚液(と全血製剤)の有効期間は採血後21日間で、2〜6℃で保存します。RBCをオーダーして届いたときはまだ冷たいですよね?ちゃんとホットライン使って温めてね😊(そのまま投与すると体温低下を招きます)
ちなみにヘマトクリットはおよそ60%です(時間と共に溶血して減っていきます。最終的には50%くらい)。
赤血球輸血の目的は、ヘモグロビンの濃度を上昇させることで、組織への酸素をきちんと運搬できるようにすることです。
重篤な合併症(虚血性心疾患など)がない限り、赤血球輸血を開始しようとなるヘモグロビンの値は7g/dl程度です。
新鮮凍結血漿(FFP)
よく現場では「白」と呼ばれるFFP。外科の先生方は出血しだすと結構安易に入れて入れてといいますが😅、一応きちんとした基準がありますよー。
1pac(2単位)は供血400ml由来でおよそ240mlです。新鮮凍結血漿というくらいですから、凍結(ー20℃以下☃️)して保存しています。凍っているため製剤としての寿命も長く有効期限は採血後1年間です。使用時には30〜37℃の温水槽でゆっくり溶かし、溶解後3時間以内に使用します。
さっさと溶けて欲しい時にいつまでもシャーベットな困った奴です😅
FFPには全ての凝固因子が含まれているため、凝固障害がある場合の補充や、ワーファリンの作用拮抗、血漿交換用やその他出血が持続する病態の治療のために用いられます。「循環血漿量増加の目的で使用してはならない」とよく言われます。
数値的な適応は、
- PT-INRが2.0以上
- aPTTが基準値の2倍以上
- PTが25%未満
- フィブリノゲンが100mg/dl未満
- (循環血液量に匹敵する大量出血がある場合)
などの場合です。
血小板濃厚液(PC)
「はたらく細胞」というコミックでも人気だった血小板ちゃんです(知らない人は検索!)娘も血小板ちゃんのファンです。
RBCやFFPに比べて通常の手術ではそうしょっちゅう使用する製剤ではないですが、肝移植や心臓血管外科(大血管)ではお馴染みだと思います。
1pac(10単位)は約200mlで、その中におよそ2.0×1011個ほどの血小板ちゃんが含まれています。保存は20〜24℃で震盪(揺らす)して保存しています。寿命はとっても短くてわずか4日です。とっても貴重な製剤なので、「(使うかわからんけど)とりあえずオーダーしとくか」なんてことを言うと輸血部や血液センターの人にタコ殴りにされます😵(しかも10単位8万円強します!高!ちなみに赤白は1万8千円くらいです)
投与基準ははっきりこれ!というものはありませんが、一般的には5万/μL程度を保つように投与されることが多いです。ただし、緊急時に出血が続いていて5万を切ってから悠長にオーダーしていると間に合わないので、血液型や輸血在庫の有無、血液センターから取り寄せる時間なども考慮してオーダーする必要があります。
補足:試験ではvon Willebrand病では血小板数が正常だが、血小板機能を来すこと、慢性のDIC(播種性血管内凝固)では血小板輸血の適応がない、ことが出題されています。
(おまけ)膠質液
膠質液を選択させる問題が出ています。
輸液には大きく分けると細胞外液、維持液、膠質液があります。
各種輸液に関する詳しいことは今後advancedで取り上げたいと思います。
- 乳酸リンゲル液(商品名:ソルラクト、ラクテックなど)
- 酢酸リンゲル液(商品名:ソルアセト、ヴィーン、フィジオ140など)
- 重炭酸リンゲル液(商品名:ビカネイト、ビカーボンなど)
- アルブミン製剤(商品名:アルブミナーなど)
- デキストラン製剤
- HES製剤(商品名:ヘスパンダー、ボルベンなど)
血液製剤の投与あれこれ
原則として血液製剤はホットラインなど温水で加温して投与します。4℃まで冷やされたものが体をめぐるとそれだけで体温が低下してしまいます(それに伴い不整脈が生じることもあります)。細胞外液のように血管外に分布しないので、常温保存の輸液よりたちが悪いです。必ず温めましょう。赤血球製剤を加温する必要性がある条件として、次のもの出題されています。
- 急速大量輸血
- 新生児交換輸血
- 寒冷凝集素を持つ患者
また、注意深く輸液製剤を見たことがあれば気づくと思うのですが、輸血製剤のラベルに「LR」や「Ir」と書いているのがわかると思います。

この「LR」は保存前白血球除去済み(Leukocytes Reduced)の略です。白血球除去により、発熱反応、白血球抗体産生に伴なう血小板輸血不応状態、サイトメガロウイルス感染の予防、原因不明の免疫抑制の予防などの効果があります。
2007年以降、赤十字血液センターから供給される輸血製剤には白血球が含まれていないため、輸血投与の際に白血球除去フィルタは必要ありません。ただし、フィブリン塊など微小凝血塊除去フィルタは必要です(通常赤血血球輸血用と比較的大量に輸血する場合に用いるものとありますので、施設で使用されているものを確認しておいてください)。
「Ir」と言うのは放射線照射済み(irradiated)の略で、GVHD(次の投稿で)の予防のための放射線照射が済んでますよという意味です。
- 輸血使用時に「同意書」忘れるな
- 輸血投与は低体温防止のため加温を(ホットラインなど)
- 赤血球濃厚液(RBC)2単位は供血400ml由来で約280ml。ヘマトクリット値は約60%
- RBCと全血輸血の寿命は21日間、2〜6℃で保存
- RBCの投与開始基準は一応7〜8g/dL。
- 新鮮凍結血漿(FFP)2単位は供血400ml由来で約240ml。全ての凝固因子を含む
- FFPの保存はー20℃以下で1年間。解凍は30〜37℃のぬるま湯で溶かして3時間以内に使用。
- FFPの適応はPT-INR2.0以上やフィブリノゲン100mg/dl未満が代表的
- 血小板濃厚液(PC)は10単位200ml。血小板数は200億個くらい。
- PCの保存は20〜24℃で震盪。寿命は4日間。
- PC投与の目安は血小板数5万/μL程度。
- 輸血投与の際に白血球除去フィルタはいらない(すでに除去済み)。微小凝血塊除去フィルタは必要。
輸血準備に関わること
ここでとりあえず知っておく必要がある用語としては以下のものがあります。不必要な輸血オーダーを減らすために②〜④がある。
- 不規則抗体
- タイプアンドスクリーン(T&S)
- 最大手術血液準備量(MSBOS)
- 手術血液準備量計算表(SOBE)
不規則抗体って何ぞや?
これに関する詳しい話はadvancedに譲りますが、不規則抗体は赤血球に対する抗体で、ABO血液型の抗A抗体、抗B抗体以外の抗体の総称です。つまり、重要なものからマイナなものまでいろいろあります。臨床的に意義がある抗体については、緊急時を除いてそれ専用の血液(適合血)を使用する必要があります。
最も有名な不規則抗体はRhです。ドラマなどでもレア血液の代名詞みたいな形で聞きますよね?「この患者、Rhマイナスです!」「何ぃ!?」みたいな😅。そのRh系の抗体もさらにC、c、D、E、eの5つが重要で、この中ではDが1番抗原性が強く、2番目に強いのがEです(頻度が一番高いのはE)。これらの抗体は遅発性の輸血副作用や、新生児の溶血生疾患の要因とされています。
と言うわけで一般的にRh陽性(+)やマイナス(ー)と言えば、RhD抗原のことを指すので頭の片隅に入れておいてください。
- 不規則抗体とは、輸血副作用にも関わる赤血球に悪さする抗体のこと(ABO不適合輸血ほどではないよ)
- 一般的にはRhD抗原のこと。たまにE抗原も。
- 輸血をする(可能性のある)患者では入院時に下記のT&Sで検査されていることがほとんどです。
タイプアンドスクリーン(T&S)
輸血血液の有効利用するための方法の1つです。ある手術をするとき、「多分輸血しないと思うけど、ひょっとしたら2単位くらい赤入れるかもな。あ、いや多分使わないと思うんやけどなぁ〜」と言う時、通常オーダーすると血液製剤は購入されてストックされます。もし必要なくなって、他の人にも回せなかったらその血液製剤は廃棄になっていまします(結構高いし、せっかくの献血が無駄になってしまいます・・😫)
具体的には
- (後述するMSBOSから算出される)予想出血量が500〜600ml以下で、
- 術中の輸血の可能性が30%以下と予想される待機手術
においてタイプアンドスクリーンが行われます。具体的には、
- 上記のような条件の時に、受血者(患者)のABO血液型(タイプ)と、不規則抗体の有無をあらかじめ調べておき、交差適合試験を行わずに血液を準備しておきます。
- この時点で(病院によるかもしれませんが)院内在庫がない場合、発注(購入)はまだしません。必要になった場合に取り寄せます。
- いざ輸血が必要になった場合には、表試験によりABO血液型を確認するか、生理食塩液法による主試験のみ行い、異常がなければ適合血として払い出し、輸血が行われます。(※表試験、裏試験、主試験、副試験に関してはまた今度取り上げます)
要は、無駄なオーダーを減らそうと言うことです。
SBOEとMSBOS・・略語ばかりで嫌になる・・!
- SBOE:手術血液準備量計算法(Surgical Blood Order Equation)
- MSBOS:最大手術血液準備量(Maximum Surgical Blood Order Schedule)
他にも覚えないかんこといっぱいあるのに、こんな略語ばっかり覚えられるかーい!😫という声も聞こえてきそうですが・・。ま、でもこういうのがある、ということはまず第一歩として覚えておいてください。
どちらも上記のタイプアンドスクリーンと同様に血液製剤を無駄にオーダー・準備することがないようにしよう!という方法の1つです。
各施設ごとに、この術式ではこのくらいの出血をしてきたというデータがありますよね。その術式別の平均出血量を調べてその1.5倍程度のクロスマッチ(交差適合試験)済みの血液を準備しようというのが、MSBOSです。ただ・・やはり準備しすぎてしまうことが多く、無駄になることも多いんですよね・・😫
そこでより現実的な方法として、SBOEが提唱されている。
- その患者が許容できる出血量を求める(術前Hbと輸血開始ラインとなるHbの値から)
- 術式別の平均出血量から①の許容出血量を引いたものを単位数に換算する。それが0.5(単位)以下であればT&Sのみのオーダーとする。
- 0.5(単位)以上であれば四捨五入して整数単位で準備する。(赤なら基本2単位〜ということになると思いますが)。
オススメの薬物ハンドブック